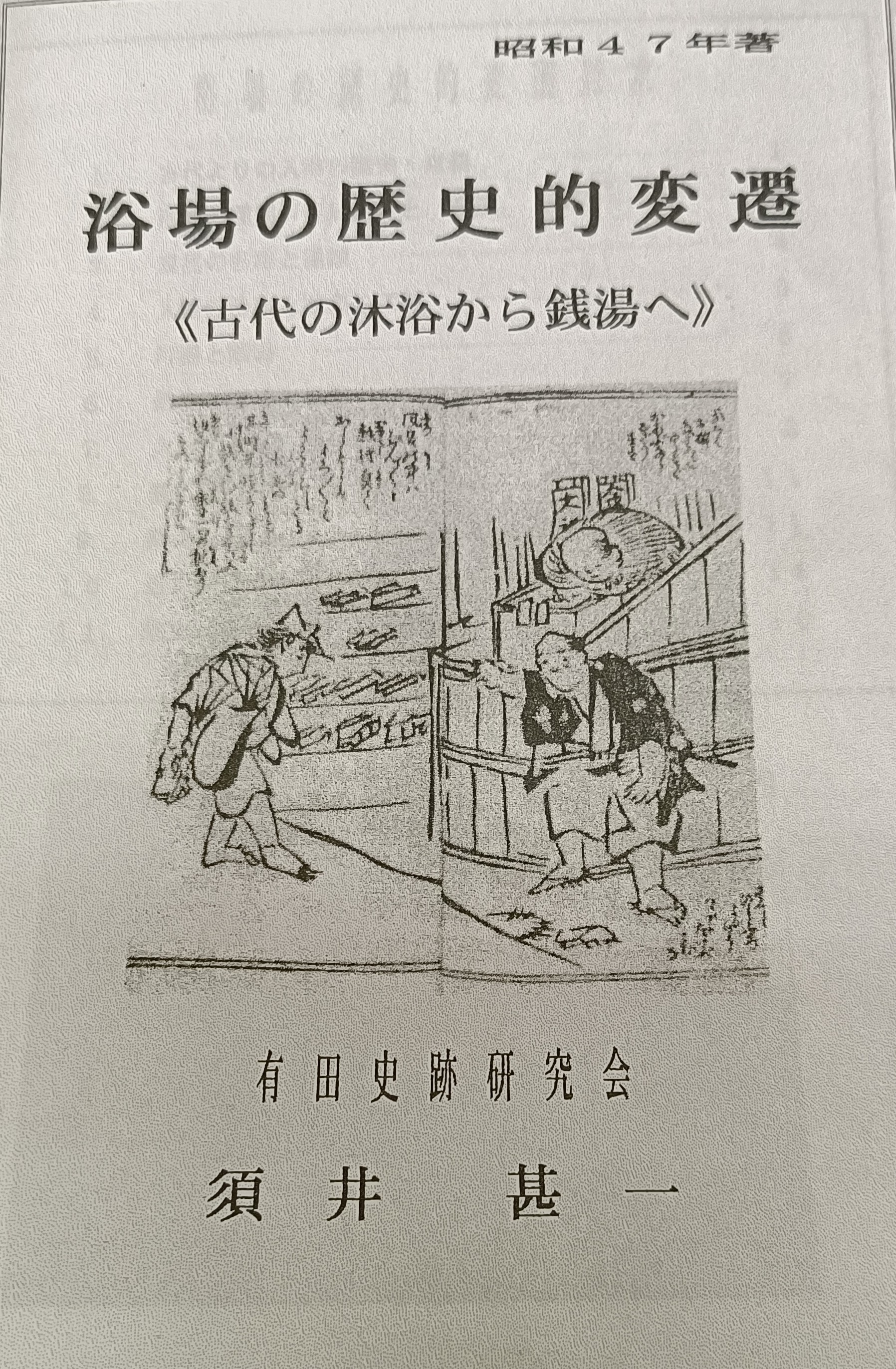
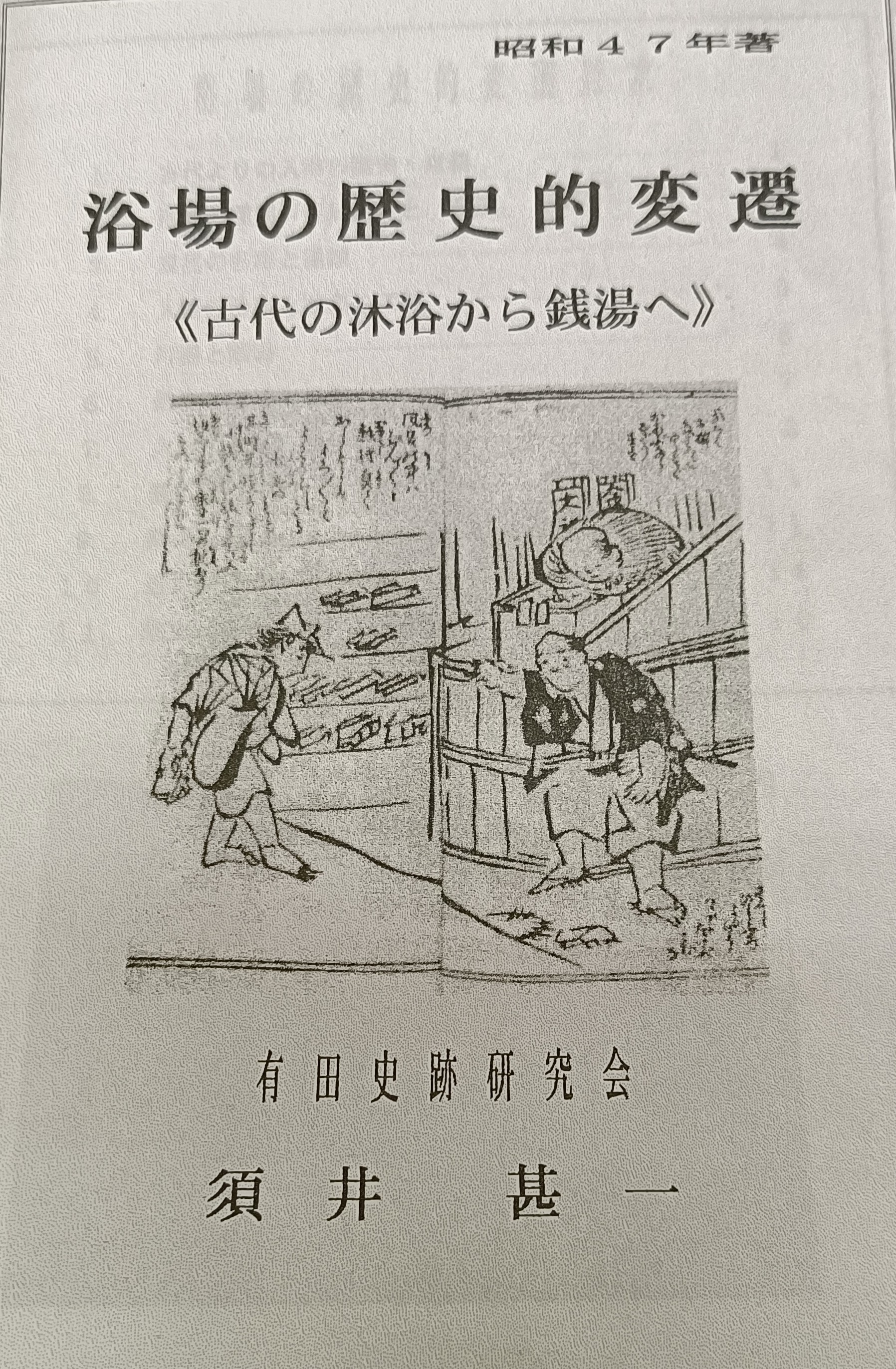
公衆浴場とは近年の呼称であって、一昔前には世人一般から「湯屋」 「風呂屋」「銭湯」と言い大衆に親しまれたものですが、わが国の原始神道の信奉以来、神霊に拝札または祈祷などの場合には洗浴して心身を清める風習は極めて古くから行なわれておりまして、中国の古書『魏志倭人伝』の中に記述されている通り、先人が死穢に際しては、家人全部が海中に入って心身を清める風習が形式化して禊となり洗浴し、更に神仏習合により或いは滝に打たれ、井戸水の給水による水垢離など信仰と祭祀の行事例式となって進化されてきた長い歴史の道であると思います。
この温冷両水の洗浴作法と一つは諸神の清潔となり、他に自ら肉体不浄を除くことともなって、一般に言う沐浴の起源とも見られるわけである。
今日でも神前での礼拝・祭祀のはじめに行なわれる修祓及び祝詞奏上の後に参列者に塩や水を掛けることは沐浴の代わりでありました。これに伴い神職が榊を左右に振って祓いとして清風に浴す、更に心身を清めるの意義を深く感ずる。
この祓いの行又は祓いは、神仏祈念奉仕には必ず行なう慣習となった平安時代から宮中では多くの御湯殿の儀と呼んで、厳かにその儀式が行なわれて天皇は浴衣を召され「天羽衣」と称する物を特に新調されて召し、宮仕人も心身を清める禊を行ったことを潔斉浴として、小沐浴又行水と称して種々の入浴法が始められたのである。
この温浴には「洗場」 と風呂という 「蒸風呂」の両方があって、その施設が互いに異なった入浴方法であったものが、後世になって混同されて「湯屋」又は「風呂屋」と呼称するようになった。
我が国に昔から渡来した外国人の「日本見聞記」にも、日本人は清潔民族にて、国民は皆入浴を好み町では銭湯に入って身体を常に清潔にするを日課とし、銭湯のない村では一枚の戸を立てて、婦女が盥で行水の姿を見かける程にて、一日の疲労を回復する楽しい日課で
あり、心身を清めることを最も尊ぶ民族であると記述している。
温浴の「洗場」と「蒸風呂」の両者について説明すると、昔の寺院伽藍の整備によって、又流派の沐浴の方法も区別されてきて、洗場は普通の湯を湯釜で沸かして浴室内で湯槽内で入浴する方法と、蒸風呂は浴室の外に大釜で湯を沸かし、この湯気を浴室の下部の簀子を通して上に送り込む、浴室内は湯気が充満して、その熱気で心身を清める蒸風呂、適当な時間に密閉室から出て流し場で、肌に浮いた垢を小笹状のもので払い落とした後に温水で洗い流す。今も残っているものに京都東禅寺の浴室・妙心寺の浴室、寺院の浴仏として仏像を洗浴させて鹿浴させ鹿垢を流し落とすとか、その代表的な行事に四月八日釈尊降誕の「灌仏会」がある。
中に医術の心得のある僧侶即ち「医僧」がおり、衆僧中病傷患者に投薬治療に当たり、その状態によって風呂治療を必要とする者にこれを勧めたとあり、町の大湯屋に洗場の風呂と蒸風呂と両設備があったことが大きな町に記録されている。有名なのが京都「東福寺」の浴室・「妙心寺」の浴室(明智風呂)・「西本願寺」に移建されているものに豊臣秀吉の「聚楽第」に設けていた「黄鶴台」のものであったとあり、
(1) 飛雲閣の黄鶴台(蒸風呂)・諸大寺の温室の風呂は、後に離宮や別荘に模倣されたとある。
(2) 湯の語源について温水を「ユ」と呼んでいる。古く神代の頃、自然に湧く温泉も「ユ」であり、沸かす湯も同じですが、温泉の方早いのであって、伊豆の国は古くから自然に涌出することから「ユイズル」と言い、これが縮まって「イズ」 伊豆の国の称名となったとあり、「出雲風土記」に神湯と呼び宮中での潔斎のため沸かし湯に入浴の場所を尊称して「御」と「殿」との漢字を使用して「御湯殿」と呼称するようになり、一般も湯殿の名は近頃まで使われるようになった。
「ユ」湯は潔斎の意味で、神事の奉仕者が湯で心身を清め潔斎することから「風呂こそ日本人の姿」なれ、湯の起こりは斉の意味で、潔斎を皇室の重大な祭事の大斉祭の悠紀が出てくる日本書紀の天武天皇の五年の条に「斉忌」という清潔の意味
最初は沐浴の方から出てきたのであって、イザナギの尊が出雲から日向のアハギ原に来られて禊をなされて以来、伊勢神宮に於いても「海水」又は「塩水」をもつて潔斎の料とする儀式あり。
摂州「有馬の湯」と紀州「裏の湯」とは古典にも記され、温湯の文字が使われ浴室、温室、温屋、湯殿・浴室・など、中世・近古の文献にあらわれてくるが、この「風呂」という語源は明らかでないが、「蒸室」から変化したものであろうか、ユアミ・浴堂を俗に「由夜」と言うこともあり、仏典に温室教なる経典もあり、後漢の安世高という人が訳した「温室洗洛衆僧経」仏典にある位だから寺院の風呂は多く、温室と称せられた。
「風呂」の語は「台」から出たということは、柳田国男氏の「郷土研究」に風呂の起源に触れ、瀬戸内海沿岸に岩風呂・竈風呂の遺風が残っていることを述べた。
欽明天皇の13年(552)友好国、朝鮮の「百済」聖明王より、仏像・経典、荘厳具と共に僧尼を贈られ、渡来帰化人も多く諸大寺院や七堂伽藍の中に「洛仏功徳経」があり、従って温室・温室院と呼称されていたことも文献にあり、これも司る役職に湯維那が略されて「湯那」は一山の事務系統を担当する僧職であり、後町風呂になると後世に「湯女」というサービスガールまで出来てくるようになった。
入浴時刻を板木の音で一山の寺内に伝え、衆僧達は座次の順に従って明衣「浴衣」 手拭・洗粉等を持参して温室の仏体に合掌して入浴する。その間湯浴の上座に敬意を表し、不潔を禁じ又高声の談声を戒め、静かに入浴し口中念仏を唱え、聞こえるものは身体を流す湯水の音のみ、温室当番は火元を点検し、厳しい掟とがあった。
安置の仏像は宗派によって異なるが、文殊菩薩・須菩薩であり、入浴規定に背くと実罰を課せられる。
「石風呂」は海岸に多く、海浜の岩窟などを応用したもの、海浜の「塩風呂」や雑木の穴の中に海藻類を加えた風呂、各地に弘法大師の発案指示のものも多く、四国の今治の東二里の処に桜井と呼ぶ土地に網敷天神より御喜浦に大きな岩窟の中に岩窟の蒸風呂があり、その入浴の心得か次のように挙げられている。
右条々は其の筋の達しにより特に御注意相成り度願上侯也。
又、旧藩政時代の梅梢院の石風呂の注意・心得に
安永九年庚子年十月日
万藤屋平文
当春より御入湯料 現銀相定申候事 安永九年
これに対して山間の地に「釜風呂」と呼ぶものがあった。京都の洛北の地「八瀬」にある釜風呂、八瀬大原付近の山野に雑木から炭焼きの考案から思いついたもので、生木を熱すると生木より発散する薬用水分を利用して熱気浴を利用する。
汗蒸の歴史は古く、壬申の乱 (672)の際、大海人皇子(後の天武天皇)は大友皇子と戦って背に矢傷を受け、その治療のためしばらくの間この地に難を避けて釜風呂で治療されたという。そのために「矢せ」の名が出来たという。又南北朝時代の初め延元元年正月に、後醍醐天皇は足利尊氏の軍勢に追われてこの八瀬の里に逃れた時、この釜風呂の中に難を避けられたとあり、「八瀬釜風呂」は江戸時代の正徳五年の調査に十六軒もあったという。
法隆寺の裏山にある一軒の家は「薬師風呂」と呼ばれ、昔から伝わる「蒸風呂」だ。外が浜の「雁風呂」は、内に石を積み置きて其の下より火を焚き、石を焼き是れに冷水を注ぎ打ち掛ける也。これにより湯煙盛んにたち充満する時入口を閉じ、中にて陸湯や冷水で顔を洗い身を清める。
又、他に「施浴」というのがある。浴を衆生に施すことで仏への祈願とかで、衆僧の潔斎として湯具の類を新に調製したものを施入する。光明皇后の立顧施浴の所伝で「法華寺」で千人の人々に施湯を催し、自ら入浴者の汚垢を落したとあり、その時代「行基菩薩」が「有馬の湯」で病人を洗った伝記があり、施浴の全盛期時代は鎌倉時代で、源頼朝も後白河法皇の追善の大法会に大施浴を行なった。百日間一日百人の往来の諸人誰でも入浴を施し、浴者の整理に奉行まで置いたと幕府日記に記している。
「雁風呂」は、大体東北に伝わるもので、小林一茶の句に「今日からは日本の雁いて楽に寝よ」 「雁風呂や海荒るる日は焚かぬなり」がある。シベリヤからの渡り鳥(雁)が日本への途中、海上で羽を休めるために浮木を聊えて渡ってくる。その落した木の枝を集めて風呂を炊くことから「雁風呂」と呼ばれるようになったと伝えられる。
5.町湯と銭湯
足利時代に生活が苦しく、自家で湯を沸かすことなく、多く町湯を利用する。多勢の人々が集まって入浴に行ったため、外の客を止めたのでこれを「止め湯」又は「止め風呂」といった。
応永八年(1401) 町湯は入浴料として銭をとったことから「銭湯」の文字が現われてきたとある。
正平七年(北朝文和元年)京都祇園社内の「岩愛寺」で銭湯の営業を始めたとあり、その前にも元享年中に「雲居寺」領内に銭湯があったことも記されている。(元亭とは後醍醐天皇時代の年号・岩愛寺より四十年も前の時代鎌倉末期に当る) 大湯矢の監督施浴の世話を担当する役を「湯維那」と称し、それが「湯那」となり、後世「湯女」の文字が見えてくる。
江戸時代は普通の町湯と遊湯風呂(湯女)がはっきり区別されていたのであって湯女のいる風呂は遊びの目的で、客を入れる現在の「サウナ」とか「トルコ風呂」のようなものと考えてもらえば、普通の町の湯屋「銭湯」と混同して考えると間違ったことになる。その当時参勤交代で諸大名の勤番家臣達が湯女風呂に通うことを禁止している記事がでている。
* 湯槽の変遷と種類 長方形(長持型)と楕円型(桶型)の二種類である。
長方型は船型であるところから「湯舟」と呼ばれる。御寺などの蒸風呂は多く、鉄釜を利用して蒸気を上げて身体を蒸したのである。宮廷の日常の湯槽は取り湯と呼んで別棟の釜殿(元湯)で浄水を沸かして御湯殿の浴槽に流し込んで入浴する。
足利時代(末期頃) 戸棚風呂というのが出来た。風呂と洗い場を兼ねた湯槽を考案して、燃料と温水の節約を考えたもので、この戸棚風呂と称するものは湯槽は横に長い長方形の木槽の上部を戸棚をかぶせたようになっていて、その戸は引き違いで、入浴の都度その戸を開閉する。湯槽の湯が少量でも、戸の密閉によって内部に湯気が充満し、その効果は充分上がった。この型のものは明治二十年頃まで残っていた。
明治時代になってから文明開化をスローガンとする新政府は、外国人の目を憚って銭湯に対して数度混浴の禁止令を出している。明治十年、神田の湯屋鶴澤紋左門が浴槽の柘榴口
(ざくろぐち)の外囲を全部取り除き、湯槽を低く下げて流し場とすれすれにして改良式風呂と称した。これが今の温泉の始まり、明治十二年十月東京警視庁令で東京府下の湯屋に柘榴口を取り外すよう達しを出した。
京橋の三十間堀の「日の出湯」という大きな湯屋が出来たのは明治十年頃、人々はこの湯を温泉と呼んで、東京では入浴料は一銭となった。それまで田舎では二文から三文が相場であった。
種類を挙げると、「釜風呂」「鉄砲風呂」「ヘソ風呂」 「五右衛門風呂」「佐渡オロGE」「長州風呂」等はいずれも家庭風呂のように小さいものであり、その様式は今でも家庭に残っている。
古い銭湯の様式である湯槽の上のかさである柘榴口の取り除きで洗う場が多くなり、湯舟に浸かっていても頭が寒いのでタオルを頭に載せることから、今でもタオルを頭に載せる習慣が残っている。
又、長崎の出島のような港では、動く風呂の舟・海に浮んだ入浴専門の湯屋舟もあった。オランダ商館の医師ツンベルクの「日本紀行」に書かれている碇泊中の船人が利用する移動式銭湯である。昔江戸の川の中にも船の銭湯があり、上方にては徳風呂という。江戸と大阪の港で便利な湯船として一回三文で人気があったとのこと、
徳川時代から銭湯の入口の構えは,「唐破風」又は「千鳥破風」の破風屋根であり、その様式是銭湯の初めは寺院の温堂や大湯にその起源があることから、構えの作りがそうなったと思う。入口の戸障子や格子の板張に《男湯》 《女湯》と書した板を掲げた。入口は土間であり、都会では下足番がおり下足棚に番号札を付けて並べたり、拍子木をたたいて時間を合図なども行なった。
東京では入浴料の他に「流し銭」 「洗髪料」が要った。番台では「手拭」「糠袋」「垢すり」 「洗粉」 「あかぎれ薬」等を売っていた。
又、番台には浴客から祝儀が贈られ、三宝に飾って喜相を祝う習慣があつた。
江戸時代には柘榴口と戸棚風呂はよく温まるので、湯からあがる時に用いる「上がり湯」又は「岡湯(陸湯)」が用意されていた。この上がり湯と冷水は、男女両浴槽の中央の境界に設けられていたものです。
「店法度書」(浴場の注意書き)
右之通御承知之上御入湯可被下候 以上
右之通御承知之れ上御入湯可被下候 以上
江戸時代、銭湯には「留め湯」というのがあるが、これは足利時代の公家寺僧等の日記に見られる留め湯とは、文字は同じでもその意味が違う。江戸時代の留め湯とは、町の家持ちとか又大店のように、多数の男女の奉公人を抱える家では、その者が入浴するごとに湯銭を払う手数を省くために、一人で日に何度入浴しても一ヶ月いくらと定めるとか、一店の奉公人何人が一ヶ月全部入浴することとして、何百文などと月極めで毎晦日に支払うのである。これは今日の乗車券の定期と同じく若干一定金額が毎月かたまっているので、至極便利だからこの留め湯即ち日定めは薬湯のような永く湯治する者に多い田舎の町では、これを「伏せ」と呼んでいた。
平安末期から鎌倉時代に始まった商工業者の権益を保護するため公家や社寺では座を設け、業者間仲間の権利が公認の座によって保護されてきた。江戸時代に度量衡の統制のため、金座・銀座・銭座更に秤座・桝座等まで設けて人々を保護し、それぞれの特権を与えた。(現在の組合)組織を仲間と呼び、江戸の各種問屋十組合大阪の二十四組合は有名である。
各仲間は規約を定め、月行事・年行事を計画して営業権の公認のため,代償として過分の冥加金を官府に納め、その保護を受けたのである。
湯屋も文化七年五月に初めて公認となった。保健衛生上又町の発展開発のため、新規営業には既設のものをおびやかさぬよう、互いに競争を避けるようにしており慶安四年二月に湯屋の売買を禁じ,湯屋の新規営業について町奉行所に願い出て、担当の与力・同心が一応書類を検討し、その後実地検分したこともある。この許可にあたっては隣接湯屋との競争を避けるために、町並みの戸数と人口を調べ、道路至便・使用水量・排水路・防火・消火のことを充分考慮している。
享保六年、八代将軍吉宗の「享保改革」にあたって、町奉行大岡越前守が諸事務の簡素化として、湯屋の新規は町名主・五人組並びに隣接各町の異義ない旨の証印を得て、同業者二・三人同行して奉行所に出頭して検討すると変わり、後に寛政二年老中松平定信の「寛政改革」について種々の制度を設け、男女混浴を厳禁している。当時湯屋は町奉行所の保護を受けていたが、仲間(組合)の湯銭の上げ下げに、更に訴訟の場合に不都合もあるところから、文化七年三月湯屋総代柳屋銀藏。高橋屋次郎右衛門・声川屋次郎兵衛の三人連名で、株仲間の冥加金の上級は不要である代わりに、無闇に湯銭を上げないことを条件として願書を提出している。この仲間公認から天保の改革までが江戸時代の湯屋太平の時、浮世床や浮世風呂と騒がれた時である。
天保五年、水野忠邦が老中となるや、世にいう「天保改革」、将軍は第十一代家斉で江戸文化華やかな時期、天保十二年三月家斉の逝去を期し、諸物価の引下げのため、都市商工業者等の独占である株仲間・問屋組合を解散させ、自由取引として新興商人達の出現を図った。このため湯屋では大人八文・小人六文であったところ大人・小人共に六文の統一値となり、八月を期して浴槽も男女別々に改造され、新規の湯屋が雨後の筍のように林立した。
江戸市中に湯屋が新設林立し、湯屋株の暴落・入浴料の値下げで、庶民生活を極度に押さえたので、不平反感が多く、商人達の反抗に抗し切れず水野老中に対する怨嗟の声高く、水野老中は辞任に追い込まれることとなった。これによって諸株仲間は漸次復旧し、嘉永四年に元株価に戻り、当時の広瀬六左衛門の雑記に、浅草馬道の湯株千五百両の沽券(売買価格)にて、一ヵ月の上り銭十両ずつの由也。日々の入浴の取り銭十四・五貫文程ずつ之有よしとあり、湯株は持ち主より借り営業する業者が、家屋土地の貸借と同じく証文と適当な敷金を入れてその権利を借りて営業するものあり。
三助というのは、今日の公衆浴場は江戸時代から世人に親しまれ、銭湯で働く男衆の呼び名である。この男衆の仲にも種々の階級があって,北の国から湯屋で働きたいと奉公した者は最初は見習いといって車を引いて燃料の運搬から下足番、二・三年をたってから釜炊き番見習いとなる。一人前になると初めて流し場に出て浴客から「三助さん」と愛称で呼ばれる番頭になる。その上番台に上がって湯銭を受けとり、お客の貴重品も預かる様になると親方の世話で湯株を手に入れて、一軒の湯屋の主人となる。
「風呂炊きの我が身は煤に成り果てて人の垢のみおとすものかな」
古今洋の東西を問わず人類は等しく長寿を願っている。
わが国でも長寿延命の法として、薬草を煎じたものを湯に入れて入浴する法がある。
鎌倉時代「万安方(よろずあんぼう)」等の医書に、諸病の治療に適応する薬湯について説いている。平安時代に僧空海(弘法大師)は京都の東寺の温堂を設けて浄湯(洗場)蒸風呂と共に薬湯を衆人に施浴したと伝えられている。
鎌倉時代に良観上人は奈良十八間戸に癩宿を設け、その中に一間半の温堂で薬草を利用した蒸風呂で治療に当ったとある。
足利時代にも玄恵法印の著「庭訓往来」の文例中にも(五木八草湯の湯治)の文献に見えている五十島とは「梅・柳・桑・桃・椿」也。又他の諾書によると「梅、 桃・桑・杉」又は「塊・柳・桃・桑・●」ともあり、葉と木皮を陰干しにして煮出すわけである。又八草も八種類の葉根を乾かしたものを用いると書いている。
安貞元年五月予病後に沐浴し、湯気散じ後過二七日也
入薬湯は、菊・桃・ヲケラ (祇園社執行日記) 文徳天皇以降常に薬となる「くこ」 をはじめ多数の草木が植えられ、江戸時代に薬園が江戸牛込に麻布・麹町・小石川植物園あり、各藩にも御用薬草園があり、江戸時代になってから草木入手困難となり、手近なものとして「柚子・無花果・楠・桃・独活・大根の葉・おおばこ・よもぎ蕎麦粉,松葉,杉葉・米糠」等が日常に使用されていた。
江戸時代、薬湯も銭湯も同じく混浴は禁止であり、明治維新になってから、平安時代からの例もあり、温泉地より原湯又は湯の花の類を運ばせてこれを炊き、温水に混ぜて保健医療であったのが、漸次娯楽清遊を目的にするに至ったもので、明治二十年頃まで各都市で繁昌していた。
この再生温泉から、西洋医学による薬品混入の文明開化薬湯営業が現われ出し、
ヨジュム温泉・カルルス泉等と名付け、明治六年五月神田雉子町に昇福亭の「西洋法薬ヨジュム温泉」の引き札を紹介する。ここの主人鶴巻紋左衛門が改良風呂とか温泉式風呂と呼び、考案者として名を残している。
現在は薬湯は禁止されていますが、昭和初期までに「中将湯」「天徳水」「カルシュウム泉」「カルルス泉」等あり、日本が海の国なるによって、昔より塩湯が医療保健に利用され、平安時代に都の貴族の中には、保養のためにわざわざ海浜で「しおあゆみ」と呼んで利用し、和歌まで残っている。又、京都まで海水を牛車で運んで、洛外の島羽離宮で塩湯を沸かして湯治をした記事がある。宇治の別荘とかで行なわれた塩湯湯治の日記は嘉承三年二月四日、藤原実資の「小石記」の中にあり、万寿三年十一月,康治二年二月九条家の玉葉にも、承安元年九月十六日に潮湯を毎日二度始むなりとある。
大永八年四月に中御門大納言と連歌師宗長等が、東海道「興津」 浜の地の宿所にて塩湯に入ったことが記されている。又連歌師里村紹巴の若狭丹後の旅日記「天橋立紀行」の中にも、六月三日文殊堂に入了、院主迎えて寺前の潮を汲ませ、焼ける風呂に入り、夕涼みになかめくらし?
塩湯の湯治場所は近世まであった。大阪の堺市の「寄宿塩風呂」もその一つで、行基菩薩の作と伝えられる、足利から江戸時代まで海辺の砂の中に横たわっていた薬師如来の石像の胸の辺より湧き出た水を沸かして万民に施浴したのが始まりで、入浴者が数日滞在したので「寄宿風呂」と呼ぶなり。
明治になり、わが国医学の恩人「ドクトル ベンツ」の教示で、保健としての海水浴を勧め、自らも家族と共に国民保健として「大磯」に海水浴場の設置を勧めた。
薬湯と銭湯は昔から仲が悪く、文政年間に訴訟を起こし、代官所で約定書まで作製している。
天然の温泉について
日本は温泉天国と呼ばれ、豊富に湯を湧出する温泉が現在千箇所以上に及んでおり、海浜に・山間渓谷に・森林地帯に太古から滾々と自然に湧出している。
伊豆の国名は「ゆいずル国」の意味で、源実朝の有名な和歌に、
「伊豆の国 山の南に いづろ湯のはやきは神のしるしなりけり」
とあるように、これを御神湯と崇めてきたことは、伊豆大島の「御神火」と呼んだ 「ように、各地に温泉明神とか薬師如来の祠堂が古くから建てられている。
湯浅小学校の近く、本町の上田酒店の西の処に土岐氏の経営する薬湯 (海草の藻を入れて)あり。湯の色は茶色の湯であったように思う。
北道に小原氏が経営する浴場 (浴場名不明)あり。小原氏ブラジル移住にしたがい入野佐太郎氏の経営となる。
北鍛冶町に永井一郎氏の「永楽湯」あり。昭和 8 年頃、熊岡氏に変わり、現在は 「黒潮湯」に改名し、石垣嘉男氏が経営している。
南鍛冶町に石惣氏の「大黒湯」が新設されたが、石惣氏が死亡して前の林七郎兵衛氏・栩野五郎氏両氏の所有に変わり、後に岩橋正雄氏が借り受けて営業せしが現在廃業に至る。
久保里の検番の裏に「山崎あんま湯」が新設してあんまさんが経営しましたが、女にだまされ恨人で死亡。幽霊が出るという噂がたって間もなく廃業。
西南道に上野徳松氏が「養老湯」を開設する。以前に今井氏がここに浴場を持っていたが、上野氏が殆ど新設の形で新装した。上野氏死亡により小川寅蔵氏に変わり現在に至る。
中川原に佐々木義信氏の「布袋湯」あり、これも明治中期に新設したもの。後に浅井道夫氏より今の森岡義楠氏に変わる。
南浜町に今井徳松氏の「末広湯」あり。今井氏は西南道の場所を上野氏に譲り、南浜町に移転して開業する。
その北、浜町の中程に宮井新助氏の「桜湯」あり。
大小路、今の横楠さんの後の家に太田仁助氏が「太田湯」を新設したが、経営振わず間もなく廃業。「大黒湯」「布袋湯」の 2 ヶ所より、5 ヵ年間保証金を出したとの記録あり。
北仲町の裏の下新町に須井藤松氏の「戎湯」あり。この「戎湯」は湯浅町で一番古く、嘉永年間以前須井甚蔵氏より続して現在で 4 代目同じ場所に経営されている。
南栄の玉置酒店の前の「つるや」の家、この場所に堀田安吉氏が「大正湯」を新設して、薬湯も併用しましたが 7 ヶ年程で宮井喜市氏に移り、大正 15 年浴場の法規が全国改正の厳しい布告となり、湯浅町の 9 軒の浴場は整備して資本を合資して会社組織を作り、6 ヶ所に整理して経営の合理化を図った。その浴場は「永楽湯・養老湯・布袋湯・大黒湯・末広湯・戎湯」の配置を考えて 6 ヶ所として発足し、3 ヶ所を整理して、株主として会社組織の中に残る。
しかし、その状況は昭和になってから時世の変化に影響されて、4 年後に南栄に横矢氏の「栄湯」が新設許可されることによって,合資会社は赤字となり離散し、元の個人経営となる。
その後に道町に山田隆一氏の「紀勢湯」の開設あり、後に竹内氏に移り現在田中弁二郎氏の経営にあり、終戦後大宮通りに中尾政雄氏の「東湯」を開業せしも、5 カ年にして廃業(原因は水質に鉄分多量)とのこと。
現在、大黒湯も廃業して旧町内には現在 7 ヶ所となり、将来まだまだ減少する傾向にあり、公衆浴場は古い歴史を残してやがて新しい時代にマッチした内容のレジャーセンターが生まれることでしょう。
当時、広川町大道に中井氏の経営する「中井湯」(広栄湯)の前、広川の東町に山下氏の経営する「山下湯」 ありしが、大正の末期に中井氏の近隣田町に醤油業戸田善吉氏が浴場を新設した。小さい町に 2 ヶ所では経営困難となり、6・7 年後に 「中井氏は廃業して、戸田氏が残り,昭和 20 年まで続いたが遂に廃業、山下氏も終戦間もなく廃業した。
「有田の奥地の浴場事情」
金屋町市場に大正時代に銭湯があり、有田川の南岸徳田に「徳金湯」、これは有田川の水害で二回も流失したが、再興して現在に残る。
吉備町の庄に個人経営の録 「湯があったのですが、地区共同経営の浴場に買収されて、今は共同浴場と変わる。
大谷には相当古くより 「大谷温泉」があり、則村氏が長く経営して今に至っている。
田栖川栖原に「栖原温泉」(千川氏経営) と浜に「七福湯」(芦内氏経営)の二軒は明治→大正→昭和と田舎の浴場として継続されている。
明治以前は田舎の銭湯は三文から五文の入浴料であったものと思う。明治中期で五厘、明治後期(明治 25 年頃)は、入浴料が 1 銭の時代は長く、互いに経営者の競争が続き、大正になっても 1 銭 5 厘は長く、ようやく大正 14 年頃に 3 銭であったと思います。この 3 銭が長く続き,昭和 13 年頃もまだ 3 銭で、県警察の厳重な監督のもとに改正の認可は昭和 13 年末か 14 年頃に入浴料 4 銭に認可されたのである。
嘉永年間より湯屋として営業を続けて現在に至るまで四代、同じ場所に今も公衆浴場を経営している「戎湯」。昔は田舎の町に湯屋営業は専業ではなく農業を営みつつ、副業として銭湯を開業した。当時の状況は一種の娯楽センターの様なもので町内の憩いの場として、仕事を終えた町の人々は風呂に入浴し、世情の話題の交流の場所として楽しみ、新聞の無かった昔はここで色々な噂を聞き、男も女も疲れを癒した長閑な場所でありました。
現在の浴場と違って、脱衣場は一部に畳の上敷を敷き詰め、大きな角火鉢を据えて皆その周
囲に座って良い気持ちになった人々が四方山の世間話を持ち寄って、中には得意の素人芸を見せる者もいたという。
これは私の祖父が私の小さい頃に話してくれた物語です。
明治維新の前に中山郷を首領とする天誅組の残党の一部が、有田の奥からこの湯浅の地に脱出して来て、海浜より熊野の奥十津川まで行くのに船待ちの間に、私の湯屋に入浴に来ました時、他の一般浴客が太刀を持った党士を恐れて近付かず困惑したとも聞いています。
其の時代の銭湯の構造はと言うと、風呂場は全部木造で浴槽は湯舟といって舟大工さんが作った大きな木の箱で、男女各々別にあり、文明開化の明治初期に男女混浴は厳しく取締りの対象になったとあり、そのため男女間を申訳の様に板で仕切ってはいますが、その板をとると男女混浴になるような仕組みに出来ていたと聞いています。
洗い場の板の間に竹で編んだ「簀」を流し場の上に敷き詰めて湯や水の流れをよくするためと、板の間流しはよく滑って危険だから、竹で編んだものは滑りを止める役もしていた。女湯は竹實の上に皆座って体を洗い、男の人は小さい腰掛けを用いたものです。女の人は糠袋を使って体を磨き,若い人は良い香りのする洗い粉の袋を使って顔などを洗う。男の人は頭の丁髷(ちょんまげ)を大切にして髪の元結である「いち」という所、紙縒り(こより)で作った「もっとり」というもので丁髷を結んでいるために湯がかかると濡れてこの紙縒りが切れると髪がざんばらになることを恐れて入浴中はあまり悪戯はせず、髷を大事にして保護したと聞いています。
当時の燃料は「松の木」 (さや)という木を割って、幾日も太陽に干して乾燥した薪木を炊いて湯を沸かしたものです。用水は大きな釣瓶で井戸の枠の周囲の、石で出来た石枠の上に乗って汲み上げ、客からの合図(拍手) を受けてから湯舟に水を入れ調節したものです。
入浴券は(湯札)といって、竹を薄くしたものに焼印を押したもので、今でも現物を保存しています。
湯舟以外に、水と湯を貯める大きな桶で出来た「水貯め」 「湯貯め」があった。
この水と湯を手杓で汲んで、上がり湯や濯ぎ水に用いたものです。
その時の注意書きが残っています。
右 湯浅警察署
大正四年七月
衛生上の取締りが出来た初めは、県条令として明治 25 年から 35 年と県警察署が衛生と風紀治安について取締りを始め、なかなか厳しかったと聞いています。
地方の警察官が各湯屋の臨検に毎日巡察に来て、先ず最初に唾壺の内を検査する。
そして、ごみ箱・銭湯の中が清潔であるかどうか、保健所が出来るまで昭和の中期まで続けられた。
大正 15 年に全国的に浴場営業に関する設備及び営業と衛生の基本的法律の改正が施行されて許可営業の制限が一層厳しくなった。
昔は浴場の湯は流しても、外部の貯水場に貯めて置くと農家の人々は田や畑に肥料として汲取に来てくれたものです。当時は石鹸や薬物が入っていない糠と人間の体の油が肥料には最適であったのでしょう。
安政の大地震の時に、津波は夜八時頃に押し寄せてきたので、先ず最初に風呂釜の火を消して、「天神山」「妙見山」 北は「すべり山」に避難し、三日間の後家に帰ったとは祖父の話。
明治の中頃に湯浅町でベストが流行し、各戸の家々の間をネズミか通るから伝染するのだから、皆家々の間をトタン板で仕切って各戸にネズミの通れないようにせよとの厳しいお達しがあり、銭湯は営業する時間に石炭酸を混入した手洗いの桶、足洗いの桶を玄関に置いて入浴に来るお客さんの足を消毒してから上に上がる様にして、敷き筵も消毒液を散布 するというなかなかの取締りであったと聞いています。