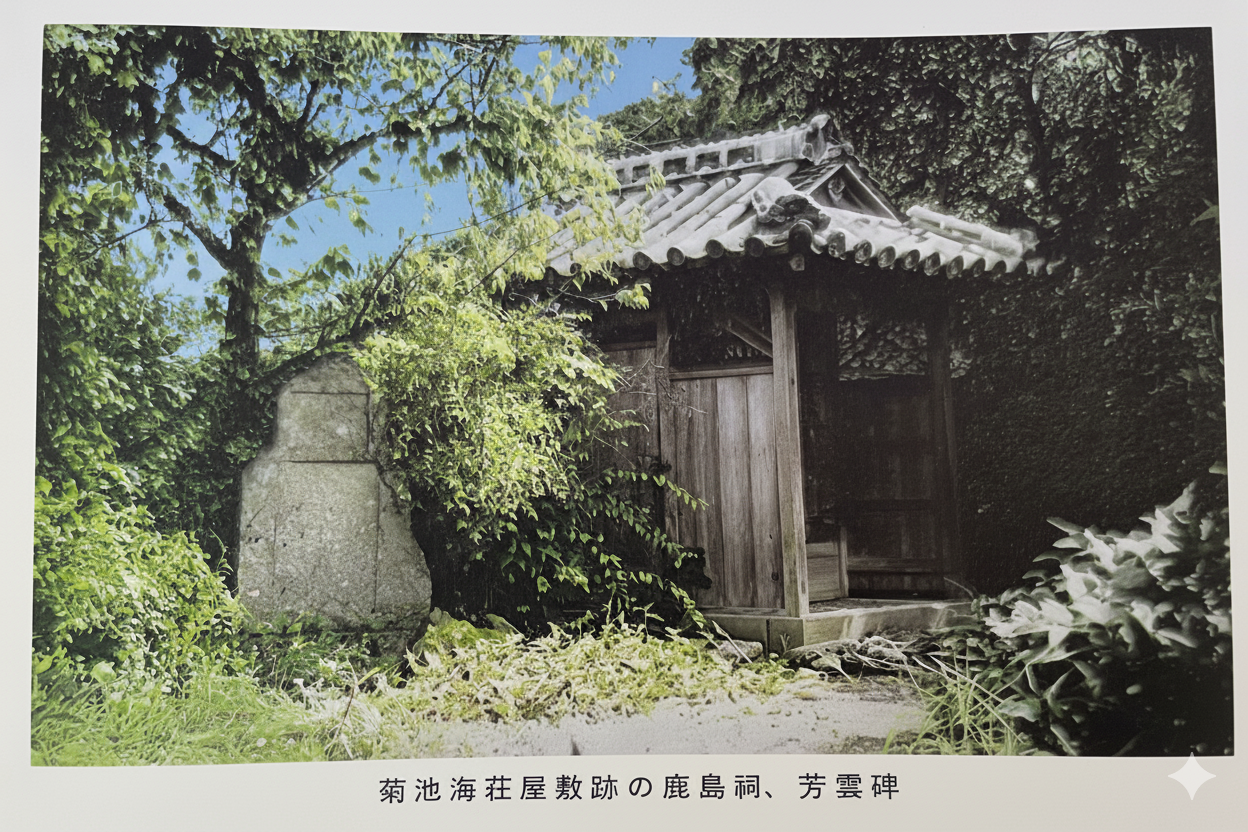一旦一区切りとしまして湯浅の60年前ぐらい前の神社シリーズあげておきます。今は当時から建替や改修されてると思いますので貴重な写真が沢山ご覧いただけるかと!!
騎馬武者(ちょっと格好よくなり過ぎ)と三面獅子は祭りも近いということで宜しくです。
深専寺 勝楽寺 福蔵寺 顕国神社 施無畏寺 国津神社 三面獅子 駆馬 満願寺
三面獅子について
場所は武内商店『かしわ』は大宮通りかな??違うか?
三面獅子の起こりは『諏訪神社』の北王城・南王城からか?・・・以下
【顯國神社の三面獅子は、湯浅町民の崇 敬を集める当社の祭礼において欠く事のできない存在である。当社の三面獅子は、毎年7月18日の若宮祭(夏祭)、 10月18日の例祭(秋祭・湯浅祭)および大晦日に顯國神社を中心に奉納される。
三面獅子がいつ頃から行われているかは不明であるが、江戸中期には湯浅中町に鎮座した諏訪神社を崇敬した湯浅の北王城・南王城(旧地名)の若衆によって 受け継がれていた。
また、この獅子が顯國神社の祭礼に参加したことは、嘉永4年(1851)の『紀伊国名所図会続編』等でも明らか である。
三面獅子は、鼻高面のオニ1人、鬼面のワニ1人、獅子2人、太鼓1人、介添えの世話役数人によって構成され、顯 國神社の夏祭及び秋祭において神輿を先導し、渡御の道行きを祓い清める役割を担う。その所作は、締太鼓のゆったりとしたテンポにあわせ、鉾を持ったオニと ワニが踊りながら魔物である獅子を鎮める古風な所作を残す。
またその芸態は、南隣の広川町・広八幡神社の「広八幡の田楽」(国選択無形民俗文化財)と、北部の有田川流域に広く分布する獅子舞との中間的な要素を示 し、中世の獅子舞の様式をとどめている。その意味で、顯國神社の三面獅子は、当地域の獅子の芸能の変遷と地域的展開を考える上で貴重な存在である。】